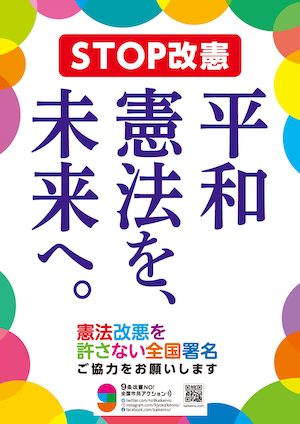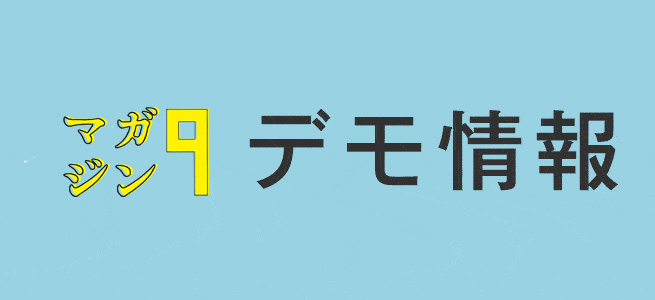公僕たちの無駄使い 〜ハコモノからデジタルへ〜
税金の無駄使いは、今に始まったことではなく、昔から "手を変え品を変え" て行われてきた。
ふた昔前までは、必要のない道路やダムの建設、環境破壊でしかない河川整備など…俗にいう「要らない公共事業」があり(今でもあると思う)、これは国政のコの字もわかっていない政治家や、地元企業に天下りしたい役人が地元に税金を引っ張ってきていた。
北海道大学の学生がまとめた「環境循環評価学特論 (番外編)」の下記レポートによると、省庁の公共事業シェアでは建設省が70%、次が農水省の20%である。
⇨公共事業論(大いなる無駄の構造)![]()
その後に続いたは税金の無駄使いは、ろくに必要性を検討しないまま無駄な施設を作る…俗にいう「ハコモノ行政」。
これは自治体が推し進め国が補助金を出した。
失敗しても責任を取る必要がない役人が、超甘い試算で事業計画を作り、その事業の是非を判断する国にしても自分のポケットからお金を出すわけじゃないので、下から上まで流れ作業でハンコを押してお金が出ていたんだろうと思う。
民間では、融資申請の半分を落とす日本政策金融公庫の審査が有名だけど、自治体や国の審査基準はどうなっているのだろう?
その後は、災害を利用した復興利権による無駄使い。
2011年に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故に関わる利権で、壮大な税金の無駄使いや中抜きが行われただけでなく、復興特別税として新たな税金も徴収された。
そして今、公僕達は最も楽に税金をかすめ取れる利権に気がついた。
それがデジタル利権である。
道路やハコモノ、災害復興などと違い、システム開発での成果物は99%以上目に見えないものである。
あるシステム開発に1000億円かかりました…と言われても、国民はその成果物を見ることができない。
成果物が見えないので、その金額が妥当だったのかどうかは判断できない。
これは、利権でいい思いをしたい政治家や役人にとっては、"濡れた手で粟"状態である。
※"濡れた手で粟" とは、何の苦労もしないで利益を得ること。
目に見えないものや価値の曖昧なもので、思い出されるのはザクっとこんな感じ。
- アベノマスク
⇨アベノマスク「送料10億円」の衝撃![]()
- コロナワクチン接種業務
⇨総額17兆円、コロナ特例支援の功罪![]()
- コロナウイルス接触確認アプリCOCOA
- コロナ特別定額給付金
⇨コロナ給付金事務費に計6700億円超…民間委託で費用膨張![]()
- マイナンバーカード
- 自治体DX (ガバメントクラウド)
国は、国民の為に直接税金を使うことは嫌がるので、必ず中抜きできる事業者や、後々キックバックがあったり、利権を構造化できる方法を考える。
ソフトウェアがハコモノよりもいいかも…ということには、10年くらい前から気がついていたと思うけど、その利権構造を描けたのがここ数年のことだったのではないだろうか。
⇨デジタル庁の勘違い
国民は目を凝らして、国を監視しなければならない。
そして、やりたい放題にさせてはいけない。
1975年に25.7%だった国民負担率は、2023年には46.8% (財政赤字を加えた本当の国民負担率は61.1%) になっている。
税金の無駄使いはとどまるところを知らず、取られる税金はウナギ登りだ。
国にはお金が余っているのに下水管のメンテナンスすらできない国…それが今の日本だ。